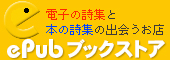夏の夜におとうとが 伊藤啓子 [詩作品]
伊藤啓子さんから送られてきた詩集『夜の甘み』(港の人)からです。
夏の夜におとうとが
伊藤啓子
薄暗い古道具屋
光の中 埃がちいさく舞っていた
わたしはくるりと振り向き
奥に座っているひとに言った
こんどは おとうとをつれてきていいですか?
奥のひとが
なんと答えたのか知らない
そこで目ざめてしまったから
着ていた白いセーラーの夏服は
モノクロにかすんでいた
けれど 夢の中の感情だけは色をおびて
くっきり浮かびあがる
そこは秘密めいた
後ろめたい場所らしかった
せめて おとうとと一緒なら
すこしは罪が軽くなると
夢の中のわたしは
ずるくおもっていた
夢の反すうは浅い眠りを狂わせる
寝返りをうちながら
せつなく おもうのは
奥にいたひとではなく
夢でも顔を見せぬ おとうと
あの店の奥に ゆるゆる
入りかける不良少女のあねの腕を
心細げに くいと引っ張る
細くあおじろい首をした おとうと
死んだ母に
一度 問うてみるべきだった
寝苦しい夏の夜
わたしにぴたりと寄り添ってくれる
おとうとを はらんだことはなかったかと
””””””””””””””””””””””””””””””””””
目ざめてみると、夢の中では、はっきり認識していた誰かのことが、はたして現実の誰だったのかどうしても思い出せなくて、一日も二日も、それ以上も、昼の時間のなかに歯がゆく立ち止まっていることがある。自分の心の中に影を落としている何かが、
だれかの形を借りて夢の中に登場するのだろうか。夢の中でさえ、心の中の影は仮面をかぶっているらしい。そうではなくて、私の中のまだ形にならない何かが、言葉となって表現されるのをもどかしく待っている姿なのかもしれない。
細くあおじろい首をした おとうととは、いったい誰なのだろう。私はよく夢の中で
部屋の隅や戸棚の奥に、長い間置き忘れられた鳥かごや、金魚鉢などを見出すことがある。そのなかには、忘れられた一羽の小鳥、むかし飼っていた小魚たちが細々と生きつないでいて、私の心を凍りつかせるのだが。
夏の夜におとうとが
伊藤啓子
薄暗い古道具屋
光の中 埃がちいさく舞っていた
わたしはくるりと振り向き
奥に座っているひとに言った
こんどは おとうとをつれてきていいですか?
奥のひとが
なんと答えたのか知らない
そこで目ざめてしまったから
着ていた白いセーラーの夏服は
モノクロにかすんでいた
けれど 夢の中の感情だけは色をおびて
くっきり浮かびあがる
そこは秘密めいた
後ろめたい場所らしかった
せめて おとうとと一緒なら
すこしは罪が軽くなると
夢の中のわたしは
ずるくおもっていた
夢の反すうは浅い眠りを狂わせる
寝返りをうちながら
せつなく おもうのは
奥にいたひとではなく
夢でも顔を見せぬ おとうと
あの店の奥に ゆるゆる
入りかける不良少女のあねの腕を
心細げに くいと引っ張る
細くあおじろい首をした おとうと
死んだ母に
一度 問うてみるべきだった
寝苦しい夏の夜
わたしにぴたりと寄り添ってくれる
おとうとを はらんだことはなかったかと
””””””””””””””””””””””””””””””””””
目ざめてみると、夢の中では、はっきり認識していた誰かのことが、はたして現実の誰だったのかどうしても思い出せなくて、一日も二日も、それ以上も、昼の時間のなかに歯がゆく立ち止まっていることがある。自分の心の中に影を落としている何かが、
だれかの形を借りて夢の中に登場するのだろうか。夢の中でさえ、心の中の影は仮面をかぶっているらしい。そうではなくて、私の中のまだ形にならない何かが、言葉となって表現されるのをもどかしく待っている姿なのかもしれない。
細くあおじろい首をした おとうととは、いったい誰なのだろう。私はよく夢の中で
部屋の隅や戸棚の奥に、長い間置き忘れられた鳥かごや、金魚鉢などを見出すことがある。そのなかには、忘れられた一羽の小鳥、むかし飼っていた小魚たちが細々と生きつないでいて、私の心を凍りつかせるのだが。
Spaceより 「石段」 坂多瑩子 [詩作品]
[SPACE」93号で坂多瑩子さんの詩を読んだ。
坂多さんの詩は、どこか独り言のようだ。それは意識の下にあるあちこちの層から、記憶の断片が勝手に顔をのぞかせ、ふたたびどこかに消えていってしまうようでもあり、それは読み手の受け止め方によって、それぞれの人のもう一つのつぶやきや、忘れられたものがりを引きだす呼び水となったりする…そんな感じがする。
石段 坂多瑩子
ひとつふたつ
一緒にかぞえてという
女医さんの声を聞きながら
石段をのぼった
体温はすこし下がっているようだった
石段をのぼりきったところには
タラもどきの木が大きく立っている
夏らしく
茂った木は勢いがあり
あかるい空に
むこうのちいさな家に
それから
自分を描きこむまえに
あたしは何も分からなくなった
気がつくと
へやの暗がりに
ベッド 空っぽだった
ネコがいなくなったネコはあれから一度も帰ってこない
一度もついてきたことのなかった石段を
ぽんぽん跳ぶように
あたしを追い越していった
あたしはネコのように
ないた ないてみたかったベッドの上で
むかし
ひとつふたつ
女医さんと一緒に数をっかぞえた
”””””””””””””””””””””””””””
石段や階段をのぼる、おりるということは、平坦な道をあるくのと違い、次元の移動というもうひとつの要素があり、ある意味で負荷〈楽しいにせよ、苦しいにせよ)を感じさせる特殊なイメージをもつ。この詩からは病気か何かで熱っぽい夢にうなされている状況をおもいうかべた。麻酔にかかるときの状態?かもといったヒトもいた。
だが、〈石段)(数える)(夢のなかの状況のような画)〈つきまとうネコのわずらわしさ)などそれぞれの断片が、どこか深い所で読み手に見え隠れする、ある物語の脈絡を感じさせ、気になる作品だった。それも私が石段や階段のイメージになぜかこだわるたちだからかもしれないが。
坂多さんの詩は、どこか独り言のようだ。それは意識の下にあるあちこちの層から、記憶の断片が勝手に顔をのぞかせ、ふたたびどこかに消えていってしまうようでもあり、それは読み手の受け止め方によって、それぞれの人のもう一つのつぶやきや、忘れられたものがりを引きだす呼び水となったりする…そんな感じがする。
石段 坂多瑩子
ひとつふたつ
一緒にかぞえてという
女医さんの声を聞きながら
石段をのぼった
体温はすこし下がっているようだった
石段をのぼりきったところには
タラもどきの木が大きく立っている
夏らしく
茂った木は勢いがあり
あかるい空に
むこうのちいさな家に
それから
自分を描きこむまえに
あたしは何も分からなくなった
気がつくと
へやの暗がりに
ベッド 空っぽだった
ネコがいなくなったネコはあれから一度も帰ってこない
一度もついてきたことのなかった石段を
ぽんぽん跳ぶように
あたしを追い越していった
あたしはネコのように
ないた ないてみたかったベッドの上で
むかし
ひとつふたつ
女医さんと一緒に数をっかぞえた
”””””””””””””””””””””””””””
石段や階段をのぼる、おりるということは、平坦な道をあるくのと違い、次元の移動というもうひとつの要素があり、ある意味で負荷〈楽しいにせよ、苦しいにせよ)を感じさせる特殊なイメージをもつ。この詩からは病気か何かで熱っぽい夢にうなされている状況をおもいうかべた。麻酔にかかるときの状態?かもといったヒトもいた。
だが、〈石段)(数える)(夢のなかの状況のような画)〈つきまとうネコのわずらわしさ)などそれぞれの断片が、どこか深い所で読み手に見え隠れする、ある物語の脈絡を感じさせ、気になる作品だった。それも私が石段や階段のイメージになぜかこだわるたちだからかもしれないが。
「キャベツのくに」から [詩作品]
またご無沙汰していました。
今日は鈴木正枝さんの「キャベツのくに」という詩集のなかから二扁の作品を挙げさせていただきます。
読むひとによっても、読む状況によっても、いろんな風に読めるこわい詩です。
月の丘 鈴木正枝
夜が来て
熱が引くと
からっぽの頭の中に
月がのぼります
無理やり束ねておいた神経が
さわさわと
枝葉を拡げ
森のように騒ぎ出す
丘の上
真昼間埋めたばかりの
寂しい私のにくしみが
見つけられそうになって
急いで目を閉じます
月あかりを消して
もう一度
深く
深く
埋めなおさなければなりません
その分だけ
重くなった身をおこし
引きずって
床にころがっている
もうひとりの人の
瞼を開いて
中を覗き込みます
あなたも何か埋めましたね
丘の上は
何年もの光のあくで
まっ蒼
見るばかりで
誰にも見られない私の月は
決してやせることなく
まあるくまあるく
破滅にむかって進みます
あなた
完璧な満月が
のぼりましたよ
”””””””””””””””””””””
破滅に向かってまあるくなっていく月…
丘の上は何年分かの光のあくで蒼く染められている…
ほんとに この地上に埋められたにくしみと寂しさの総量を、天上の月が
照らし出したら、どういうことになるでしょうか。
もう一つ詩を挙げます。
松は 鈴木正枝
松は
数ヶ月の潜伏期間を
ひとりで耐えた
数百匹の虫たちは
内へ内へと潜入していったが
松は
すべてを明け渡しながら
ついに松であることをやめなかった
予定されていた
その時が来たとき
耐えてきた緑を
ふつりと断ち切り
断ち切った痛みに
松は
初めて小さく叫びながら
そのままの形で物になっていった
物になったまま
物として
松は
松であり続けた
きっかりと潔く
夕陽のような赤を
野に流して
松は
今日は鈴木正枝さんの「キャベツのくに」という詩集のなかから二扁の作品を挙げさせていただきます。
読むひとによっても、読む状況によっても、いろんな風に読めるこわい詩です。
月の丘 鈴木正枝
夜が来て
熱が引くと
からっぽの頭の中に
月がのぼります
無理やり束ねておいた神経が
さわさわと
枝葉を拡げ
森のように騒ぎ出す
丘の上
真昼間埋めたばかりの
寂しい私のにくしみが
見つけられそうになって
急いで目を閉じます
月あかりを消して
もう一度
深く
深く
埋めなおさなければなりません
その分だけ
重くなった身をおこし
引きずって
床にころがっている
もうひとりの人の
瞼を開いて
中を覗き込みます
あなたも何か埋めましたね
丘の上は
何年もの光のあくで
まっ蒼
見るばかりで
誰にも見られない私の月は
決してやせることなく
まあるくまあるく
破滅にむかって進みます
あなた
完璧な満月が
のぼりましたよ
”””””””””””””””””””””
破滅に向かってまあるくなっていく月…
丘の上は何年分かの光のあくで蒼く染められている…
ほんとに この地上に埋められたにくしみと寂しさの総量を、天上の月が
照らし出したら、どういうことになるでしょうか。
もう一つ詩を挙げます。
松は 鈴木正枝
松は
数ヶ月の潜伏期間を
ひとりで耐えた
数百匹の虫たちは
内へ内へと潜入していったが
松は
すべてを明け渡しながら
ついに松であることをやめなかった
予定されていた
その時が来たとき
耐えてきた緑を
ふつりと断ち切り
断ち切った痛みに
松は
初めて小さく叫びながら
そのままの形で物になっていった
物になったまま
物として
松は
松であり続けた
きっかりと潔く
夕陽のような赤を
野に流して
松は
林檎ランプ 尾崎まこと [詩作品]
今日は尾崎まことさんの新しく出された大人のための童話集『千年夢見る木』から
短い詩を一篇入れさせていただきます。
これは文庫本くらいの大きさのハードカヴァーの本で、表紙の色が鮮やかな黄色、
左子真由美さんの挿絵もきれいです。”9つの夢の贈り物”と表紙にあります。
最初の頁をめくると次のような文が目に入ります。
「この宇宙はほんとうは美しい図書館です。なのに大きすぎて
その入口が分からないと、もどかしく思ったことはありませんか。
あなたは、不思議で驚きに満ちた、大切なその一冊に違いありません。
この小さくて黄色い本がその扉になってくれたらうれしいです。」
(著者)
林檎ランプ
尾崎まこと
林檎山の林檎の木
風が吹くと
まだ青くて小さいけれど
鈴なりの子どもたちが
かりん こりん かりん
いい香りで鳴ります
昼間は見えないけれど
一つ一つのまんなかには
小さな炎が
灯っているのです
夜になると皮をすかして
ほんのり明るむので
林檎山全体まるで
輝く童話の森のようです
林檎ランプは
夕焼けの空と同じように
だんだん水色からピンクへ
ピンクから茜色に偏光し
私たちのために美しく
美味しく熟していくのです
今年の秋
ナイフでさくっと割っていただく時
林檎ランプ
つまりそのまんなか
灯し続けた炎のあとを
たしかめてこらんなさい
””””””””””””””””””””””””””””
夜になると、皮を透かして、中心にある林檎の芯が炎のように内側から明るんで
来るので、林檎山全体が闇の中でほんのりと輝くという描写、林檎を食べるとき
燃え尽きた炎の痕をたしかめてごらん…というところ、すばらしいイメージで林檎
一個が自分の中でよみがえってきて、この柔らかな感性に共鳴してしまいます。
それからこの小さな一冊の童話集が宇宙の図書館の入り口である…という哲学的
イメージに触れると、ああ、そうか…この自分もその蔵書の一冊だったのだと
気がついて、自分という存在のかけがえのなさを感じさせられるのは、不思議な
ことばの力です。
短い詩を一篇入れさせていただきます。
これは文庫本くらいの大きさのハードカヴァーの本で、表紙の色が鮮やかな黄色、
左子真由美さんの挿絵もきれいです。”9つの夢の贈り物”と表紙にあります。
最初の頁をめくると次のような文が目に入ります。
「この宇宙はほんとうは美しい図書館です。なのに大きすぎて
その入口が分からないと、もどかしく思ったことはありませんか。
あなたは、不思議で驚きに満ちた、大切なその一冊に違いありません。
この小さくて黄色い本がその扉になってくれたらうれしいです。」
(著者)
林檎ランプ
尾崎まこと
林檎山の林檎の木
風が吹くと
まだ青くて小さいけれど
鈴なりの子どもたちが
かりん こりん かりん
いい香りで鳴ります
昼間は見えないけれど
一つ一つのまんなかには
小さな炎が
灯っているのです
夜になると皮をすかして
ほんのり明るむので
林檎山全体まるで
輝く童話の森のようです
林檎ランプは
夕焼けの空と同じように
だんだん水色からピンクへ
ピンクから茜色に偏光し
私たちのために美しく
美味しく熟していくのです
今年の秋
ナイフでさくっと割っていただく時
林檎ランプ
つまりそのまんなか
灯し続けた炎のあとを
たしかめてこらんなさい
””””””””””””””””””””””””””””
夜になると、皮を透かして、中心にある林檎の芯が炎のように内側から明るんで
来るので、林檎山全体が闇の中でほんのりと輝くという描写、林檎を食べるとき
燃え尽きた炎の痕をたしかめてごらん…というところ、すばらしいイメージで林檎
一個が自分の中でよみがえってきて、この柔らかな感性に共鳴してしまいます。
それからこの小さな一冊の童話集が宇宙の図書館の入り口である…という哲学的
イメージに触れると、ああ、そうか…この自分もその蔵書の一冊だったのだと
気がついて、自分という存在のかけがえのなさを感じさせられるのは、不思議な
ことばの力です。
またなの [詩作品]
久しぶりで更新します。今年前半も間もなく過ぎようとしています。2月から3月にかけて足の手術で入院するなどして、ずいぶんペースが遅れました。今日は中井ひさ子さんの「ブランコのり9号」からの作品を載せたいと思います。
またなの 中井ひさ子
こんな日は
考える人になって と
公園のベンチに座っていたら
昨日言ってしまった
ひと言が
からだのすき間から
聞こえてきて
ちりちり 痛いよ
またなの と
ラクダが
けむたげな目をして
通り過ぎていく
冷たいね
春だもの
微かに揺れている
桜も 木蓮も 菫も 大根の花も
とり集めて見よう
見渡せば
風の
大仰な身振り手振りで
もっと もっと
思い出してしまったよ
ぼくの
こぶの中にあるものなあに
帰ってきた
ラクダが聞いた
””””””””””””””””””””””””””
少ない語彙なのに、というかそのために、呼吸のリズムがびんびん伝わり、現実味を感じてしまう。とくにラクダ(中井さんのなかの一因子?)が生きている。一人称が(ぼく)で登場するのが印象的。(俺)とか(私)に入れ替えて見ると、空気が一変するのでおもしろかった。彼女はここですっと(ぼく)にしたのかなあ。今度きいてみよう。
またなの 中井ひさ子
こんな日は
考える人になって と
公園のベンチに座っていたら
昨日言ってしまった
ひと言が
からだのすき間から
聞こえてきて
ちりちり 痛いよ
またなの と
ラクダが
けむたげな目をして
通り過ぎていく
冷たいね
春だもの
微かに揺れている
桜も 木蓮も 菫も 大根の花も
とり集めて見よう
見渡せば
風の
大仰な身振り手振りで
もっと もっと
思い出してしまったよ
ぼくの
こぶの中にあるものなあに
帰ってきた
ラクダが聞いた
””””””””””””””””””””””””””
少ない語彙なのに、というかそのために、呼吸のリズムがびんびん伝わり、現実味を感じてしまう。とくにラクダ(中井さんのなかの一因子?)が生きている。一人称が(ぼく)で登場するのが印象的。(俺)とか(私)に入れ替えて見ると、空気が一変するのでおもしろかった。彼女はここですっと(ぼく)にしたのかなあ。今度きいてみよう。
草地の時間(村野美優詩集) [詩作品]
寝床のふね
村野美優
このあいだまで
赤土色のふとん袋を
ねぐらにしていたうさぎたちが
いつのまにかここに移動してきて
しずかな夜の海を
一緒に渡るようになった
ひたひた
へやの扉をあけると
畳まれたふとんの上で
しずかに船出を待っている
もやい綱を解くように
ふとんをひろげて横になる
わたしの背骨は竜骨になる
甲板にはうさぎが二匹
へさきには時の船頭が乗る
ひたひた
へやの扉を越えて
いきものたちの寝息のなかを
今日も寝床のふねが行く
あたらしい草たちが
聞き耳を立て
伸びていく
村野さんがうさぎ二匹と暮らしていることは、聞いていたので、彼女の日々の暮らしの一場面が
目に浮かんでくる。もっともうさぎと暮らしていたからって、こんな広々とした?たのしい詩が生まれる
わけじゃないですよね。この詩集全体から、村野さんの原感覚とも言うべき、この世界への感受の仕
方が伝わってきます。身辺のどんな存在とも(植物や動物たち、そして空間や時間とも)溶け合い、
一緒になれる共生感覚が、自然に溢れ出していて、詩人てこういう人のことをいうのでは…と、頁を
ひらくたび思ってしまう、そんな詩集でした。まさに草地の時間を感じました。もう一つ載せます。
藍色のうさぎ
白いうさぎと
茶色いうさぎが
やってきた晩
わたしはうさぎの夢を見た
夢のなかにはうさぎが三匹いた
白いうさぎと
茶色いうさぎと
藍色のうさぎ
藍色のうさぎは
わたしの胸の穴の深みに
長いこと棲んでいたので
すっかりかたちをなくしていたが
白いうさぎのあたまを撫でると
藍色のうさぎもよろこんで目を細めた
茶色いうさぎが葉っぱを食べると
藍色のうさぎの腹も満たされた
二匹のうさぎが寄り添って眠ると
藍色のうさぎもうっとりとなった
藍色のうさぎは
ときどき胸の穴から抜けだし
どこかへ行こうとした
だが自分がどこへ行きたいのか
わからないようだった
ただ夢のなかで藍色に広がり
ぼんやりと漂うだけだった
この詩は私の一番好きな作品でした。このような具体的なやさしい表現で、人が生きていることの
あてどなさや、存在感、そして愛の感情やその意味を表現されたことに打たれます。
村野美優
このあいだまで
赤土色のふとん袋を
ねぐらにしていたうさぎたちが
いつのまにかここに移動してきて
しずかな夜の海を
一緒に渡るようになった
ひたひた
へやの扉をあけると
畳まれたふとんの上で
しずかに船出を待っている
もやい綱を解くように
ふとんをひろげて横になる
わたしの背骨は竜骨になる
甲板にはうさぎが二匹
へさきには時の船頭が乗る
ひたひた
へやの扉を越えて
いきものたちの寝息のなかを
今日も寝床のふねが行く
あたらしい草たちが
聞き耳を立て
伸びていく
村野さんがうさぎ二匹と暮らしていることは、聞いていたので、彼女の日々の暮らしの一場面が
目に浮かんでくる。もっともうさぎと暮らしていたからって、こんな広々とした?たのしい詩が生まれる
わけじゃないですよね。この詩集全体から、村野さんの原感覚とも言うべき、この世界への感受の仕
方が伝わってきます。身辺のどんな存在とも(植物や動物たち、そして空間や時間とも)溶け合い、
一緒になれる共生感覚が、自然に溢れ出していて、詩人てこういう人のことをいうのでは…と、頁を
ひらくたび思ってしまう、そんな詩集でした。まさに草地の時間を感じました。もう一つ載せます。
藍色のうさぎ
白いうさぎと
茶色いうさぎが
やってきた晩
わたしはうさぎの夢を見た
夢のなかにはうさぎが三匹いた
白いうさぎと
茶色いうさぎと
藍色のうさぎ
藍色のうさぎは
わたしの胸の穴の深みに
長いこと棲んでいたので
すっかりかたちをなくしていたが
白いうさぎのあたまを撫でると
藍色のうさぎもよろこんで目を細めた
茶色いうさぎが葉っぱを食べると
藍色のうさぎの腹も満たされた
二匹のうさぎが寄り添って眠ると
藍色のうさぎもうっとりとなった
藍色のうさぎは
ときどき胸の穴から抜けだし
どこかへ行こうとした
だが自分がどこへ行きたいのか
わからないようだった
ただ夢のなかで藍色に広がり
ぼんやりと漂うだけだった
この詩は私の一番好きな作品でした。このような具体的なやさしい表現で、人が生きていることの
あてどなさや、存在感、そして愛の感情やその意味を表現されたことに打たれます。
サーラの木があった [詩作品]
以倉紘平さんの詩集『フィリップ・マーロウの拳銃』のなかから、好きな詩をひとつ載せさせていただきたい。
サーラの木があった
駅に着くと
サーラの木があった
思い出せるのはただそれだけである
そこからいかなる言葉も紡がれようがなかった
こころみるとすべて作りごとのような気がしてくるのである
〈駅〉とは何だろうそれはこの世のことではあるまいか
〈着く〉とは何だろうそれは遠い所から
この世に生まれたことを意味しているのではあるまいか
サーラには匂いと色があったはずだ
甘い花のかおり
風がにおいを運んできたのだろう
(風はひろびろとした野の方に過ぎさったのか
びっしりとつまった街の家並みのほうへ吹きすぎたのか)
そう書くともう汚れてしまう感じなのだ
たくさんの小さな花
朝日に輝いていたのか夕映えにきらめいていたのか
(乗客の中に行商のおばさんが
少女が乗っていたのかどうか
だいいち駅名や時刻表があったのかどうか)
そんなことを考えるともう嘘のような気がしてくるのである
だから
なにか豊かなものがあったとしかいいようがない
白い花の色とかおり
すみやかに時が流れ
あっという間だった
この世のことはもうそれ以外に
ぼくはなにも思い出せないのである
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
この詩集は装丁にも粋な題名にも、心ひかれた。 サーラの木とは、あの沙羅双樹の沙羅の木のこと。お釈迦さまが亡くなられたとき、いっせいに花開き、降り注ぎ、その死を悲しんだと言われる木である。朝開き夕べにはしぼむという、その一日花は夏椿とも呼ばれてる白い美しい花である。
私は、以倉さんの詩にはいつも深いところでの心の共振のようなものを覚えている。「人が生きている…その根源にある大きな感情に触れることができ、さらにそのかなたへと思いを運んでくれるような…」と、私は手紙に書いた気がする。そして、そのかなたとは、ふしぎに懐かしい場所なのだ。
彼のこの前の詩集『プシュバ・ブリシュティ』のなかにもサーラの木のことが出てくる。
その”〈サーラ〉という語”という詩のなかから一部を引用したい。
(きれはししか思い出せない夢がある。気分情緒しか残っ
ていない夢もある。たしかに見た夢でありながら、わたしの
意識にひとたびものぼることなく忘れられた夢は、誰に
所属しているのだろう。そのときの夢はどこを旅してい
るのだろう。ことばの及ばぬ内面世界のはるかな時空だ
ろうか。それは日常の世界を越えて旅するもう一人の私
である。意識の上に突如としてのぼってくることばは、
未知の領土を 旅するもう一人の私からの通信である。/……
宇宙樹サーラは、 その枝葉のやみに青い地球を抱えている。/
人間はサーラの花散る宇宙 をよぎる旅人である)
サーラの木があった
駅に着くと
サーラの木があった
思い出せるのはただそれだけである
そこからいかなる言葉も紡がれようがなかった
こころみるとすべて作りごとのような気がしてくるのである
〈駅〉とは何だろうそれはこの世のことではあるまいか
〈着く〉とは何だろうそれは遠い所から
この世に生まれたことを意味しているのではあるまいか
サーラには匂いと色があったはずだ
甘い花のかおり
風がにおいを運んできたのだろう
(風はひろびろとした野の方に過ぎさったのか
びっしりとつまった街の家並みのほうへ吹きすぎたのか)
そう書くともう汚れてしまう感じなのだ
たくさんの小さな花
朝日に輝いていたのか夕映えにきらめいていたのか
(乗客の中に行商のおばさんが
少女が乗っていたのかどうか
だいいち駅名や時刻表があったのかどうか)
そんなことを考えるともう嘘のような気がしてくるのである
だから
なにか豊かなものがあったとしかいいようがない
白い花の色とかおり
すみやかに時が流れ
あっという間だった
この世のことはもうそれ以外に
ぼくはなにも思い出せないのである
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
この詩集は装丁にも粋な題名にも、心ひかれた。 サーラの木とは、あの沙羅双樹の沙羅の木のこと。お釈迦さまが亡くなられたとき、いっせいに花開き、降り注ぎ、その死を悲しんだと言われる木である。朝開き夕べにはしぼむという、その一日花は夏椿とも呼ばれてる白い美しい花である。
私は、以倉さんの詩にはいつも深いところでの心の共振のようなものを覚えている。「人が生きている…その根源にある大きな感情に触れることができ、さらにそのかなたへと思いを運んでくれるような…」と、私は手紙に書いた気がする。そして、そのかなたとは、ふしぎに懐かしい場所なのだ。
彼のこの前の詩集『プシュバ・ブリシュティ』のなかにもサーラの木のことが出てくる。
その”〈サーラ〉という語”という詩のなかから一部を引用したい。
(きれはししか思い出せない夢がある。気分情緒しか残っ
ていない夢もある。たしかに見た夢でありながら、わたしの
意識にひとたびものぼることなく忘れられた夢は、誰に
所属しているのだろう。そのときの夢はどこを旅してい
るのだろう。ことばの及ばぬ内面世界のはるかな時空だ
ろうか。それは日常の世界を越えて旅するもう一人の私
である。意識の上に突如としてのぼってくることばは、
未知の領土を 旅するもう一人の私からの通信である。/……
宇宙樹サーラは、 その枝葉のやみに青い地球を抱えている。/
人間はサーラの花散る宇宙 をよぎる旅人である)
影の鳥(Shadow Birds) [詩作品]
影の鳥
水野るり子
鳥は死んでから
だんだんやせていくのです
町には窓がたくさんあって
夜になるとどの窓のおくにも
橙色の月がのぼります
でもお皿の上の暗がりには
やせた鳥たちが何羽もかくれています
鳥たちは
お皿の上にほそい片足を置いて
大きな影法師になって
月のない空へ舞い上っていくのです
死んだ鳥たちは
雨の降りしきる空で
びっしょりぬれた卵を
いくつもいくつも生むのです
そうして冷たい片足を伸ばして
沈んでいく月をのぞくと
深いところには
人間がいて
窓のなかで
ちぢんださびしい木を切っています
Shadow Birds
(Translated by Edwin A.Cranston)
Birds after dying
gradually grow thin
In the town there are many windous
Deep in every one at night
an orange moon rises
But in the dark on the platter
a flock of thin birds hids
Each bird stands
with one thin leg on the platter
becomes a large, black shadow
leaps toward a moonless sky
The dead birds
in the rain-gusting sky
lay dripping-wet eggs
clutch after clutch
And each stretching out one cold leg
they peer at the sinking moon
In a deep place
are humans
inside windows
cutting shrunken, lonely trees
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
「影の鳥」 は初期の作品です。一枚の画を描くような気持ちで自分のなかの
イメージを詩にしました。詩集『ヘンゼルとグレーテルの島』 に入れました。
水野るり子
鳥は死んでから
だんだんやせていくのです
町には窓がたくさんあって
夜になるとどの窓のおくにも
橙色の月がのぼります
でもお皿の上の暗がりには
やせた鳥たちが何羽もかくれています
鳥たちは
お皿の上にほそい片足を置いて
大きな影法師になって
月のない空へ舞い上っていくのです
死んだ鳥たちは
雨の降りしきる空で
びっしょりぬれた卵を
いくつもいくつも生むのです
そうして冷たい片足を伸ばして
沈んでいく月をのぞくと
深いところには
人間がいて
窓のなかで
ちぢんださびしい木を切っています
Shadow Birds
(Translated by Edwin A.Cranston)
Birds after dying
gradually grow thin
In the town there are many windous
Deep in every one at night
an orange moon rises
But in the dark on the platter
a flock of thin birds hids
Each bird stands
with one thin leg on the platter
becomes a large, black shadow
leaps toward a moonless sky
The dead birds
in the rain-gusting sky
lay dripping-wet eggs
clutch after clutch
And each stretching out one cold leg
they peer at the sinking moon
In a deep place
are humans
inside windows
cutting shrunken, lonely trees
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
「影の鳥」 は初期の作品です。一枚の画を描くような気持ちで自分のなかの
イメージを詩にしました。詩集『ヘンゼルとグレーテルの島』 に入れました。
鳥(Bird) [詩作品]
鳥
水野るり子
空のまんなかで
凍死するのがいる
雹にうたれて
胴体だけで
墜ちてくるのがいる
ふいに
空で溺れかける
瞬間の鳥が
恐怖の足でつかむ
はじめての空
その空の深度へ
首はすでに
首だけのスピードで
落ちはじめている
Bird
E.A.Cranston訳
There’s one that freezes to death
in midair
There’s one that’s a headless body
falling to death
beaten by hail
Caught by surprise
drowning in the sky
instantly the bird
clutches with the feet of fear
its first sky
Out of the depth of that sky
its head has already begun
at the speed of head alone
to fall
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
これは第一詩集「動物図鑑」に載せた作品です。
五月頃、はげしい雹に撃たれて落ちる鳥がいるという事をきいて書いた作品です。
水野るり子
空のまんなかで
凍死するのがいる
雹にうたれて
胴体だけで
墜ちてくるのがいる
ふいに
空で溺れかける
瞬間の鳥が
恐怖の足でつかむ
はじめての空
その空の深度へ
首はすでに
首だけのスピードで
落ちはじめている
Bird
E.A.Cranston訳
There’s one that freezes to death
in midair
There’s one that’s a headless body
falling to death
beaten by hail
Caught by surprise
drowning in the sky
instantly the bird
clutches with the feet of fear
its first sky
Out of the depth of that sky
its head has already begun
at the speed of head alone
to fall
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
これは第一詩集「動物図鑑」に載せた作品です。
五月頃、はげしい雹に撃たれて落ちる鳥がいるという事をきいて書いた作品です。
オーロックスの頁・(The Aurochs Page) [詩作品]
オーロックスの頁
水野るり子
この地上が 深い森に覆われ
その中を オーロックスの群れが
移動する丘のように 駆けていたころ
世界はやっと 神話のはじまりだったのか
貴族達が 巨大なその角のジョッキに
夜ごと 泡立つ酒を満たし
ハンターたちが 密猟を楽しんでいたころ
世界はまだ 神話のつづきだったのか
やがて 森は失せ
あの不敵な野牛たちは滅びていった
うつろな杯と 苦い酔いを遺して
破り取られた オーロックスの長いページよ
世界は それ以来 落丁のままだ
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
(オーロックスは長い角をもつ大きな野牛であり、飼牛の祖先だった。ユニコーン伝説のもとになり
旧約聖書にも登場する。角はジョッキとして珍重され、肉は食べられ、1627年に最後の1頭が死んだ)
The Aurochs page
( Edwin A.Cranston訳)
The earth was covered in dense forest
through it roamed herds of aurochs
like moving hills maybe the world at last
was entering the time of myth
When nobles every night filled giant horns
to overflowing with the frothy mead
and hunters took their sport in poarching game
maybe the world was still in myth’s continuum
Finally the forest vanished
those intrepid wild oxen followed into oblivion
leaving hollow drinking cups and a bitter intoxication
the long aurochs page torn out the world’s book
has ever since been incomplete
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
(この作品は以前「夢を見てるのはだれ?」という葉書詩のシリーズに発表したものです。一部訂正しました。)
水野るり子
この地上が 深い森に覆われ
その中を オーロックスの群れが
移動する丘のように 駆けていたころ
世界はやっと 神話のはじまりだったのか
貴族達が 巨大なその角のジョッキに
夜ごと 泡立つ酒を満たし
ハンターたちが 密猟を楽しんでいたころ
世界はまだ 神話のつづきだったのか
やがて 森は失せ
あの不敵な野牛たちは滅びていった
うつろな杯と 苦い酔いを遺して
破り取られた オーロックスの長いページよ
世界は それ以来 落丁のままだ
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
(オーロックスは長い角をもつ大きな野牛であり、飼牛の祖先だった。ユニコーン伝説のもとになり
旧約聖書にも登場する。角はジョッキとして珍重され、肉は食べられ、1627年に最後の1頭が死んだ)
The Aurochs page
( Edwin A.Cranston訳)
The earth was covered in dense forest
through it roamed herds of aurochs
like moving hills maybe the world at last
was entering the time of myth
When nobles every night filled giant horns
to overflowing with the frothy mead
and hunters took their sport in poarching game
maybe the world was still in myth’s continuum
Finally the forest vanished
those intrepid wild oxen followed into oblivion
leaving hollow drinking cups and a bitter intoxication
the long aurochs page torn out the world’s book
has ever since been incomplete
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
(この作品は以前「夢を見てるのはだれ?」という葉書詩のシリーズに発表したものです。一部訂正しました。)