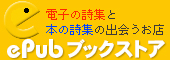ヘイデン・カルースの詩 [言葉のレンズ]
急に猛暑になってぐったり。夜、八木幹夫さんに拝借したヘイデン・カルース(1921年アメリカ・コネティカット州生れ)の詩集「雪と岩から、混沌から」(沢崎順之助訳)を読む。氷点下の厳しい寒さのつづくヴァーモント州北部の冬から生まれてきたというこれらの詩は、自然のただなかを生きる生活者のきびしい精神と張り詰めた美しさを感じさせ、この程度の熱帯夜にげんなりした私の気持ちを洗い直してくれた。鉱物のようなかっきりとした手触りをもつ彼の作品を紹介したい。まず一篇目を。
夜の雌牛
今夜の月は満杯の盃のようだった。
重たくて、暗くなるとすぐ
靄のなかに沈んだ。あとに
かすかな星が光り、道ばたの
ミルクウィードの銀色の葉が
車の前方に輝くだけだった。
それでも夏のヴァーモントでは
夜のドライブがしたくなる。
山奥の闇のような靄のなか、
褐色の道路を走っていくと
まわりに農場が静かに広がる。
やがてヤナギの並木が途切れて、
そこに雌牛の群れが見えた。
いま思い出してもどきっとするが、
闇のなか間近で深々と呼吸していた。
車を停め、懐中電灯をつけて
牧場の柵まで行くと、雌牛は
寝そべったまま顔を向けた。
闇のなかで悲しい美しい顔をしていた。
数えると——四十頭ばかりが
牧場のあちこちにいて、いっせいに
顔を向けた。それは遠い昔の
無垢だった娘たちのように
悲しくて、美しかった。そして
無垢だったから、悲しかった。
悲しかったから、美しかった。
ぼくは懐中電灯を消したが、
そこを離れる気はしなかった。
といってそこでなにをするのか
分からなかった。その大きな
闇のなかで、はたしてなにが、
ぼくになにが、分かっただろう。
柵に立ちつくすうちに、やがて
音もなく雨が降りはじめた。
夜の雌牛
今夜の月は満杯の盃のようだった。
重たくて、暗くなるとすぐ
靄のなかに沈んだ。あとに
かすかな星が光り、道ばたの
ミルクウィードの銀色の葉が
車の前方に輝くだけだった。
それでも夏のヴァーモントでは
夜のドライブがしたくなる。
山奥の闇のような靄のなか、
褐色の道路を走っていくと
まわりに農場が静かに広がる。
やがてヤナギの並木が途切れて、
そこに雌牛の群れが見えた。
いま思い出してもどきっとするが、
闇のなか間近で深々と呼吸していた。
車を停め、懐中電灯をつけて
牧場の柵まで行くと、雌牛は
寝そべったまま顔を向けた。
闇のなかで悲しい美しい顔をしていた。
数えると——四十頭ばかりが
牧場のあちこちにいて、いっせいに
顔を向けた。それは遠い昔の
無垢だった娘たちのように
悲しくて、美しかった。そして
無垢だったから、悲しかった。
悲しかったから、美しかった。
ぼくは懐中電灯を消したが、
そこを離れる気はしなかった。
といってそこでなにをするのか
分からなかった。その大きな
闇のなかで、はたしてなにが、
ぼくになにが、分かっただろう。
柵に立ちつくすうちに、やがて
音もなく雨が降りはじめた。